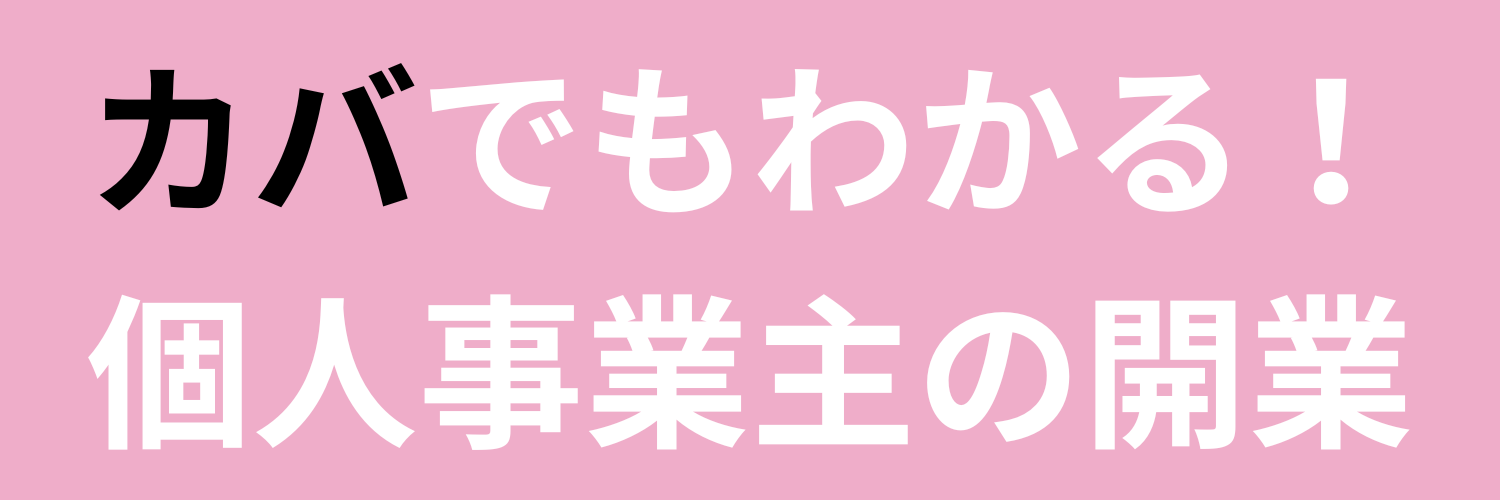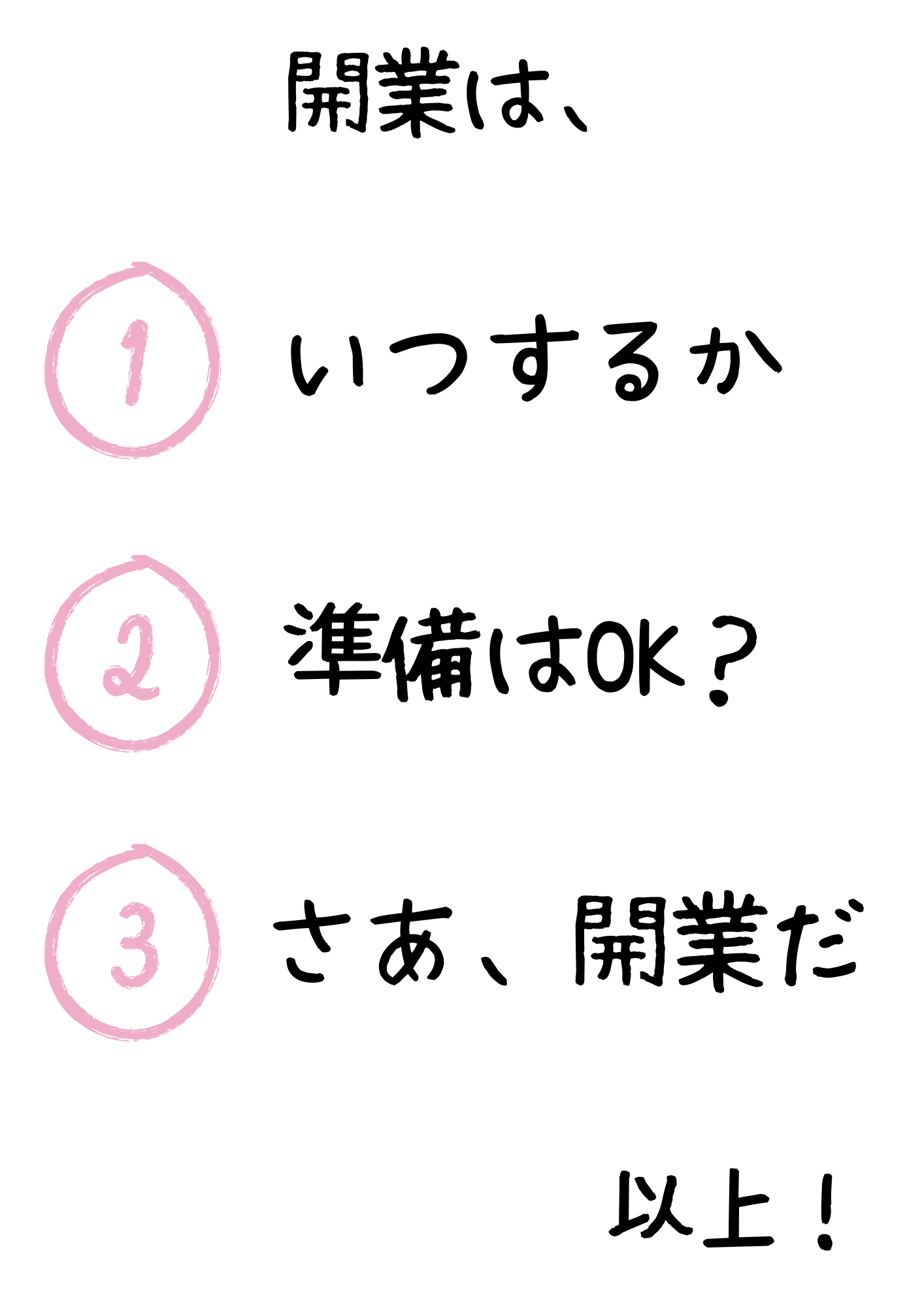
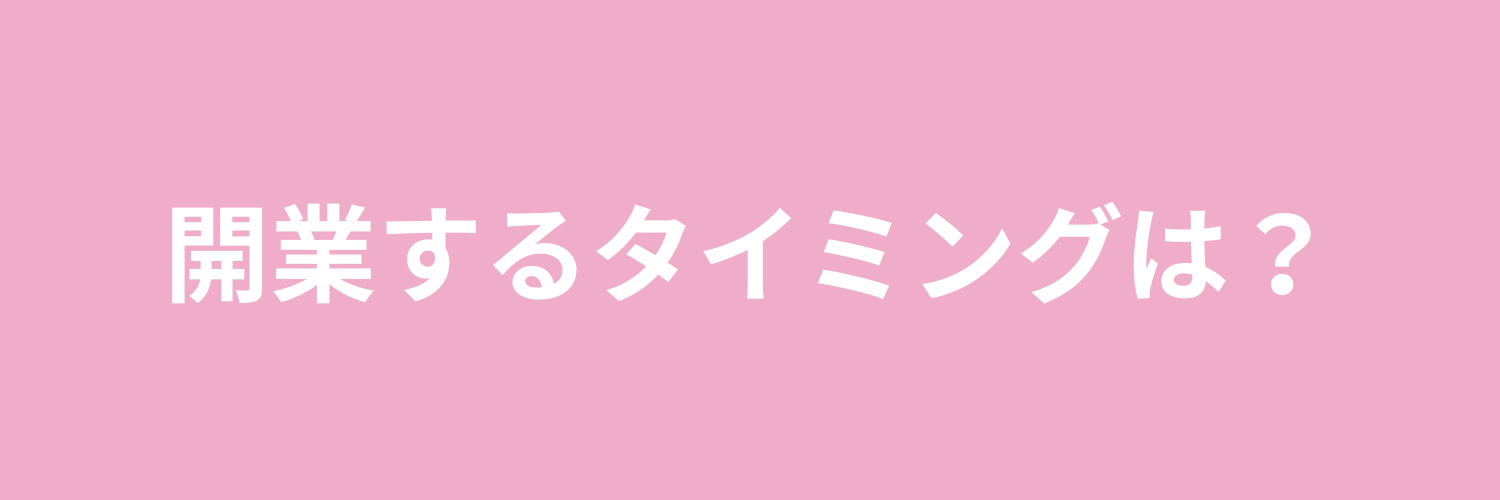
- 副業でいくら稼いだら開業すればいい?
- 開業っていつでもできるの?
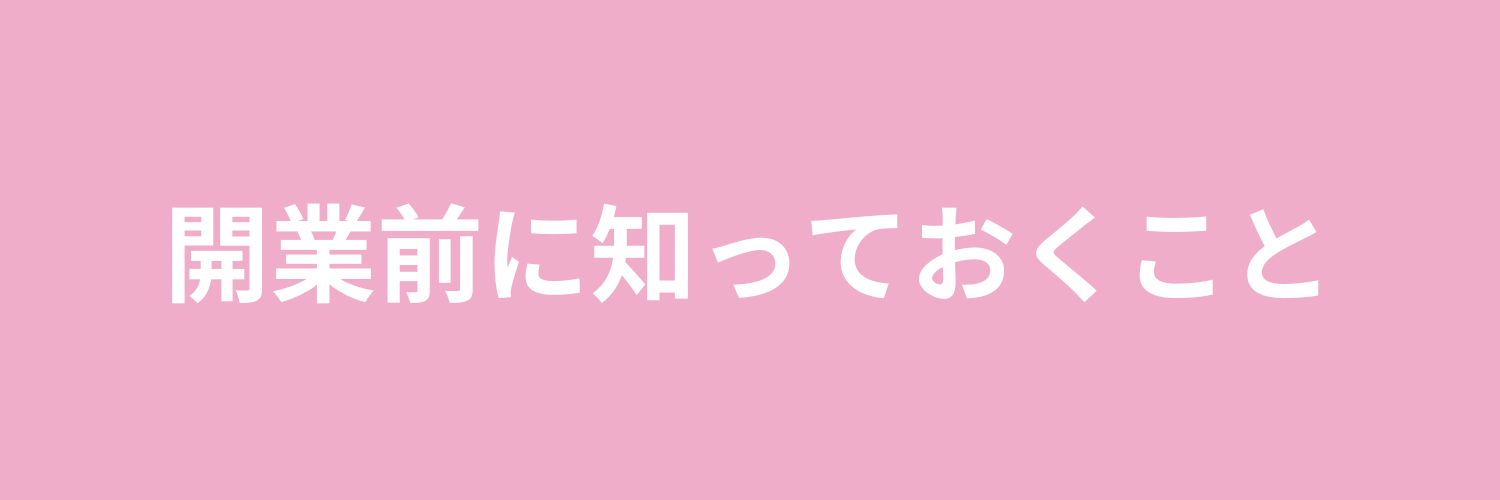
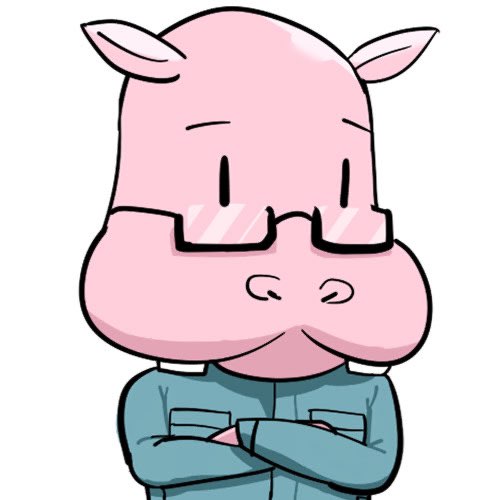
カバ山親方
「知ってる / 知らない」で損をするかもしれないよ!
\ 「カバでもわかるシリーズ」へGO!! /

詳しくはこちら
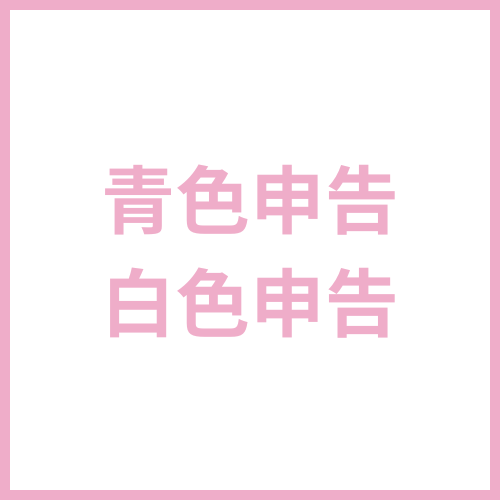
詳しくはこちら
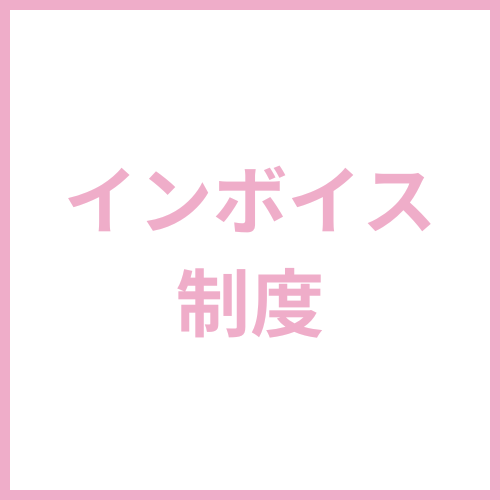
詳しくはこちら

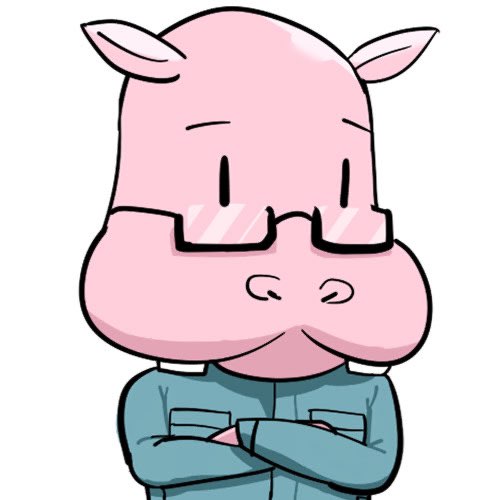
カバ山親方
大切なのはスモールスタート!
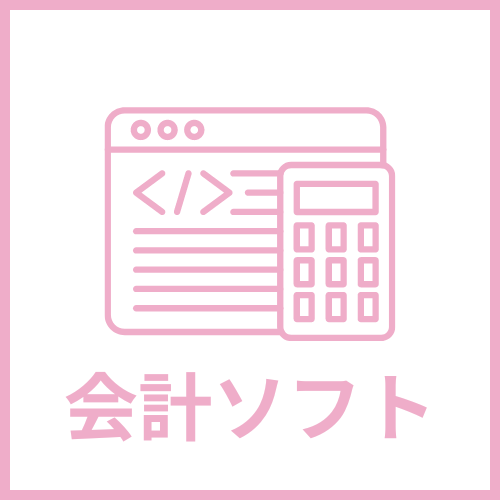
詳しくはこちら
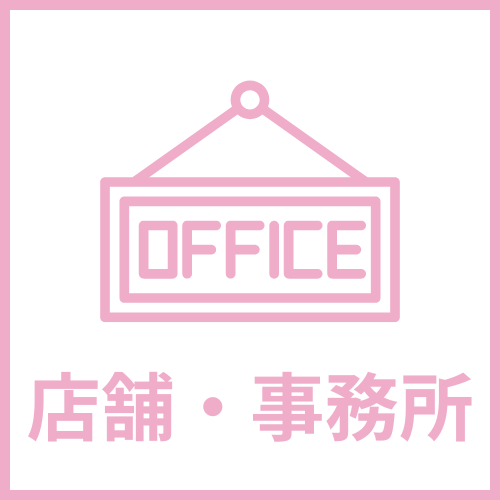
詳しくはこちら
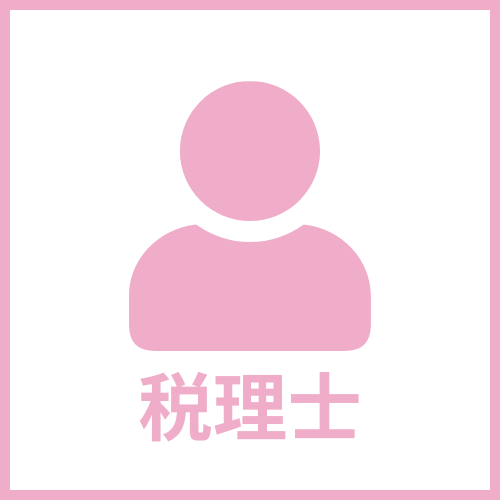
詳しくはこちら
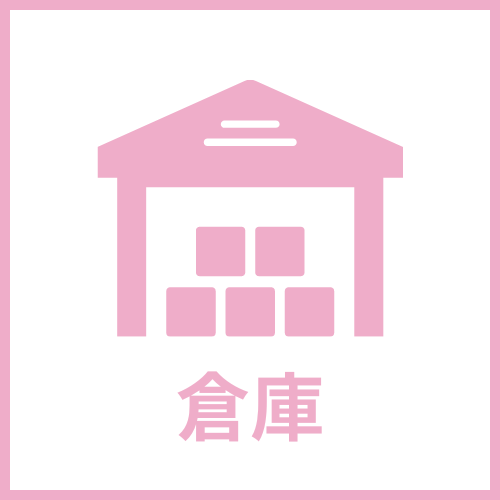
詳しくはこちら
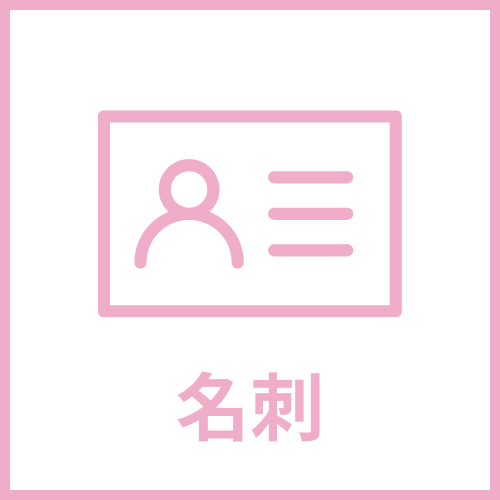
詳しくはこちら
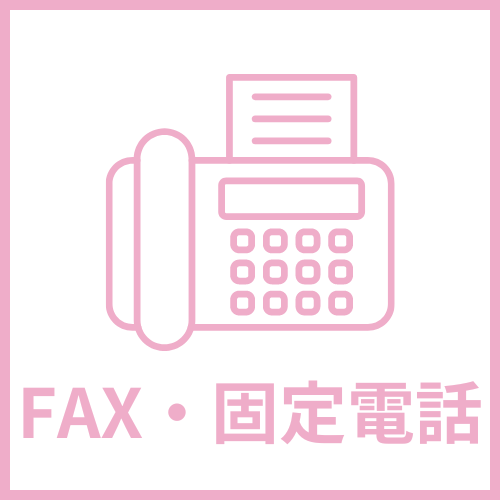
詳しくはこちら
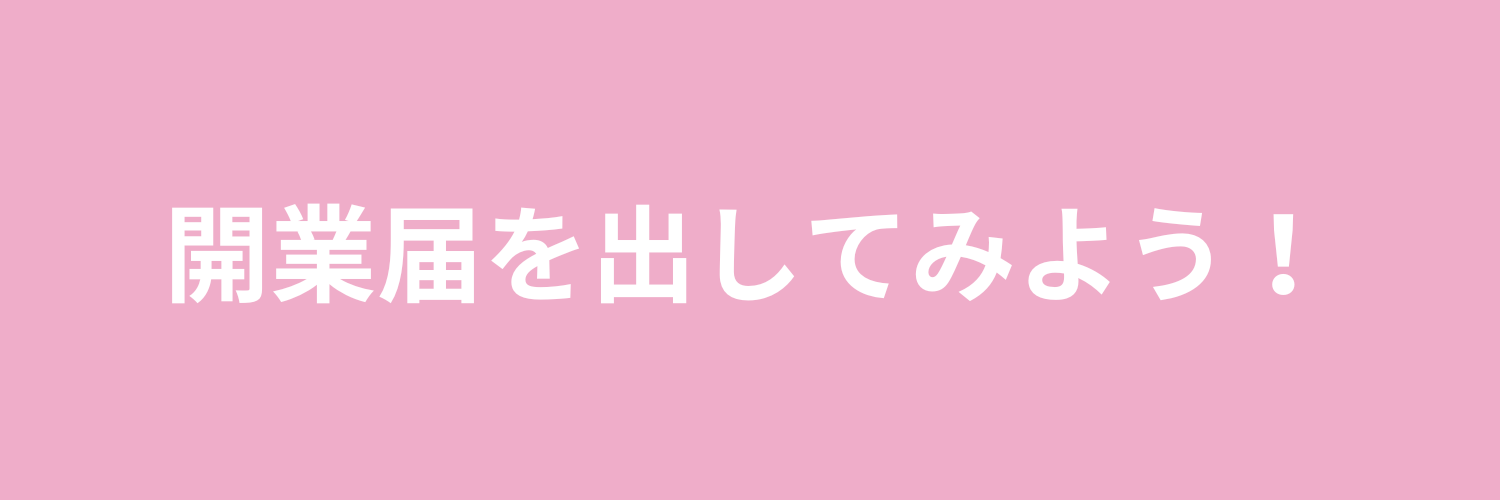
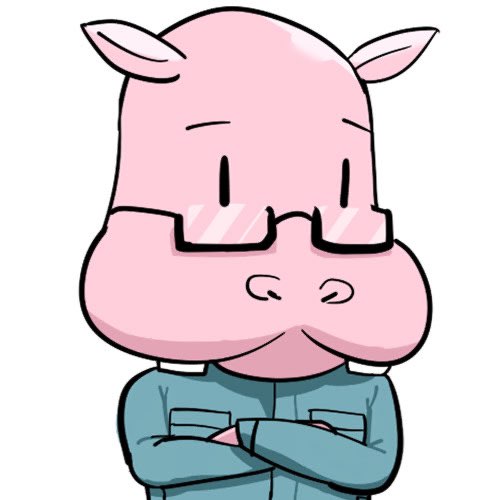
カバ山親方
開業書類はこの6つ!
| 開業書類 | いつ | 書き方 |
| 開業届 | 開業するとき | 書き方 |
| 青色申告承認申請書 | 確定申告を青色申告 にしたいとき | 書き方 |
| 青色専業者給与に関する届出書 | 専従者の給与を 青色専従者給与にしたいとき | 書き方 |
| 給与支払事務所等の開設届出書 | 給与を支払う(従業員を雇う)とき | 書き方 |
| 源泉所得税の納期の特例の 承認に関する届出書 | 源泉所得税の支払いを まとめて(年2回)行いたいとき | 書き方 |
| 適格請求書発行事業者登録申請書 | インボイス(適格請求書)を発行したいとき | 書き方 |
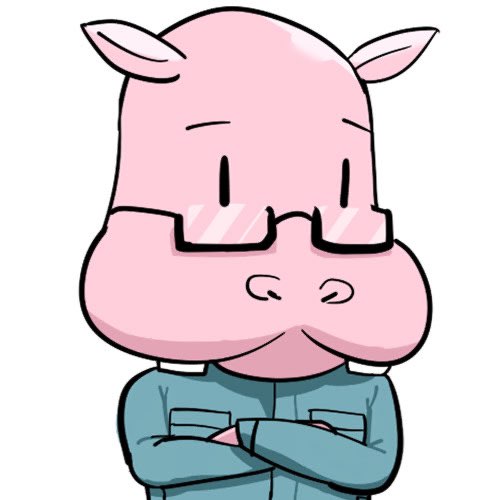
カバ山親方
さあ、個人事業主になろう!